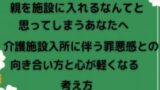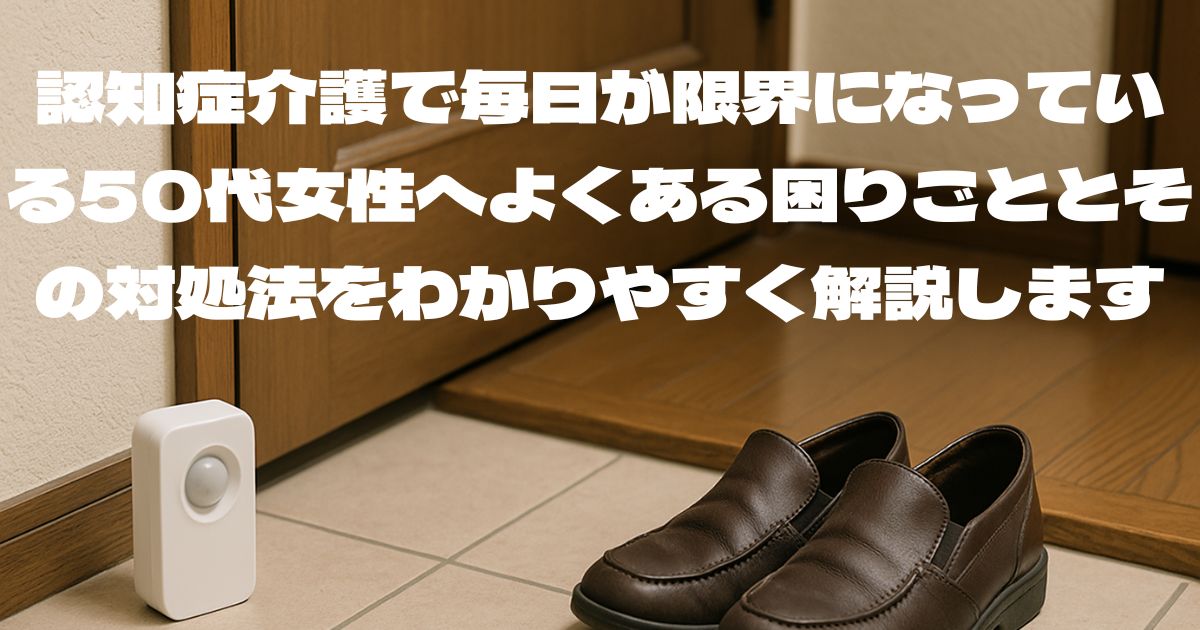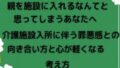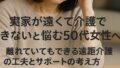「財布がない、あんたが盗ったんでしょ」
「さっきご飯食べた?」「そんなの食べてないよ」
「トイレに行ったのに、また漏らしてしまった」
認知症の親の介護をしていると、言葉では言い表せない疲れや戸惑い、不安に日々直面します。
特に50代女性は、自分自身の体調変化や仕事・子育て・親の老いなど、複数の課題が重なる時期です。
この記事では、認知症介護でよくある困りごと(BPSD:周辺症状)と、その具体的な対処法を、初心者でも理解しやすい言葉でまとめています。
今まさに悩んでいる方の心が、少しでも軽くなりますように。
結論 認知症介護は「うまくいかなくて当たり前」と考えることが大切です
認知症の症状は人によって異なり、完璧に対応できる方法は存在しません。
だからこそ、「すべてを解決しよう」とせず、「今日は少し落ち着いて過ごせた、それだけで十分」という気持ちで向き合うことが、介護者自身を守る第一歩になります。
認知症介護が特に大変と感じる理由
認知症介護は、身体的な介助よりも心の負担が大きいと言われています。
その理由は主に3つあります。
- コミュニケーションがうまくいかない
- 同じことを何度も繰り返す
- 感情のコントロールが難しくなる
さらに、「あんなにしっかりしていた親が…」という喪失感や悲しみが介護者の中に積もっていきます。
この感情の揺れをひとりで抱え込んでしまうと、介護うつや共倒れのリスクが高まります。
よくある困りごと①「物盗られ妄想」への対応方法
もっとも多くの家庭で見られるのが「財布がない」「あんたが盗ったんでしょ」といった物盗られ妄想です。
これは、記憶障害によって自分がどこにしまったかを忘れてしまうために、他人を疑うという行動に現れるものです。
対処のポイント
- 真っ向から否定しない
「私は盗っていないよ」と反論すると、かえって疑念が強まってしまいます。 - 共感しながら探すふりをする
「それは大変。いっしょに探してみようね」と声をかけ、一緒に探すことで安心させることができます。 - 決まった場所にしまう習慣を作る
たとえば財布なら、引き出しに箱を置き「ここに入れようね」と一緒に確認することで、トラブルを減らせます。
ポイントは「事実よりも、本人の不安を受け止めること」です。
よくある困りごと②「徘徊」への対応方法
夜中に玄関を開けて出て行こうとする、昼間ふらっと外に出て行って帰れなくなる…。
徘徊は家族にとって心配の尽きない行動のひとつです。
これは、「トイレに行きたい」「家に帰るつもり」など、本人にとっては理由がある場合もあります。
対処のポイント
- 出入り口にチャイムや見守りセンサーを設置する
夜間の徘徊に気づけるようにするだけでも安心感が変わります。 - 出かけたがる理由を探る
たとえば「仕事に行かなくちゃ」という言動があるなら、「今日はお休みの日だよ」と伝えることで落ち着く場合もあります。 - 靴や鍵を目立たない場所に移動する
手に届くところにあるとすぐ外に出てしまうため、工夫することで行動を予防できます。
徘徊は叱るのではなく、「安心してもらう」「行かなくて大丈夫だと納得してもらう」ことが大切です。
よくある困りごと③「同じことの繰り返し」への対応方法
「ご飯食べた?」「いつ帰るの?」「今日は何日?」といった、同じ質問の繰り返しもよくある行動です。
一日に何十回も同じ会話が続くと、介護者の方が気が滅入ってしまうことも…。
対処のポイント
- 質問されるたびに「初めてのように」答える
疲れますが、本人は本当に「初めて聞いている」と感じています。 - 日めくりカレンダーや写真、ホワイトボードを活用する
「今日は〇月〇日」「お昼ご飯は済みました」といった視覚情報を増やすことで、安心につながります。 - 返事が面倒なときは、うなずくだけでもOK
疲れているときは、短く「うん」「そうだね」だけでも十分です。無理をしないことが一番大切です。
よくある困りごと④「暴言・暴力」への対応方法
「バカ」「出て行け」など、認知症による人格変化が出るケースもあります。
中には、叩く、押すなどの暴力行為が出る場合もあります。
これには、本人の中にある「不安」「恐怖」「混乱」が影響しています。
対処のポイント
- 距離を取って安全を確保する
まずは自分の身を守ることが第一です。近づきすぎないことが大切です。 - 原因となるきっかけを探る
声かけのタイミングや、トイレ・空腹・寒さなどの不快感が原因になっていることもあります。 - すべてを受け止めようとしない
暴言や暴力に耐え続ける必要はありません。必要であれば、訪問看護や医師、地域包括支援センターに相談しましょう。
「介護者が傷つくべきではない」ことを忘れずに、自分を守ることを優先してください。

認知症介護を支える外部のサポートを活用する
認知症介護には、制度や支援を上手に使うことが不可欠です。
以下のようなサービスをぜひ検討してみてください。
- デイサービス(通所介護)
日中だけ施設で過ごすサービス。家族のリフレッシュにもなります。 - ショートステイ(短期入所)
1泊から利用可能。冠婚葬祭や休養のために便利です。 - 認知症カフェや介護者の会
同じ悩みを持つ人とつながることで、孤独感が和らぎます。 - ケアマネジャーに相談して、適切なケアプランを立ててもらう
「限界になる前に助けを求める」ことは、やさしさの証です。
まとめ 完璧な対応より、親子が少しでも穏やかに過ごせる工夫を
認知症介護は、毎日が予測できず、思い通りにいかないことばかりです。
でも、「すべてをうまくやること」ではなく、「今日をなんとか乗り切れた、それで十分」と思うことが、あなたの心を守る力になります。
最後に、今回の内容をふりかえります。
- 認知症介護では心の疲れがたまりやすい
- よくある困りごと(妄想・徘徊・暴言・反復行動)には、共感・工夫・距離感が効果的
- 外部サポートや制度を遠慮なく活用することが、介護者の健康を守る
- 完璧を目指さず、できることをできる範囲で行う姿勢が大切
あなたは、すでに十分にがんばっています。
どうか、自分の気持ちも大切にしながら、無理なく続けられる介護を選んでいきましょう。