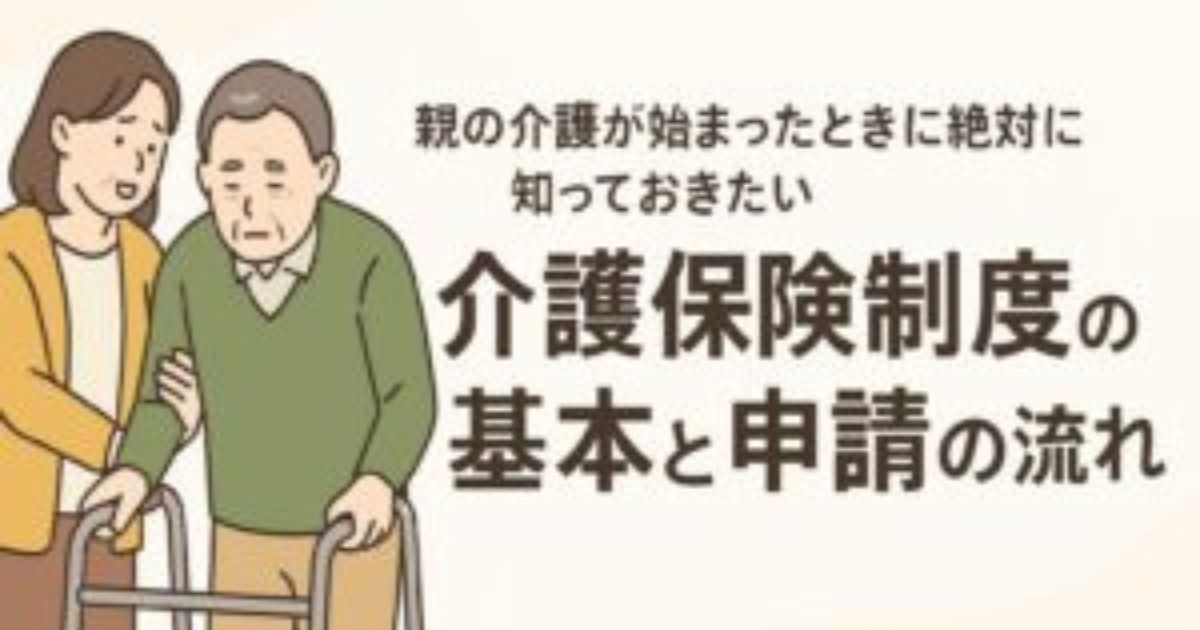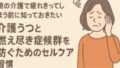「介護って、どうやって始めればいいの?」「何を申請すればいいのか分からない…」
そんなふうに感じている方も多いのではないでしょうか。
突然、親の介護が必要になると、まず関わることになるのが「介護保険制度」です。
でも、制度は専門用語が多くて難しく感じますよね。特に50代女性の方にとっては、仕事や子育てと並行して情報を集めるのは大変です。
この記事では、介護保険制度の基本と申請の流れを、初心者の方にもわかりやすく解説します。
まず結論からお伝えします
介護が必要になったら、まず「要介護認定の申請」をして、介護保険サービスを使える状態にしましょう。
この手続きをすることで、訪問介護・デイサービス・福祉用具のレンタルなどが自己負担1~3割で利用できるようになります。
申請せずに民間サービスを利用すると、すべて自己負担になってしまう可能性があるため、制度を正しく使うことが大切です。
介護保険制度とは?基本のしくみをおさえましょう
介護保険制度は、「家族だけに介護を任せるのではなく、社会全体で支え合おう」という考えのもと、2000年にスタートした制度です。
日本に住む40歳以上の方が保険料を支払い、いざというときに支援を受けられる仕組みになっています。
ポイントは、次の3つです。
- 利用するには「要介護認定」が必要
- 利用者の自己負担は原則1〜3割
- 支給されるのは「現金」ではなく「介護サービス」
つまり、「お金がもらえる制度」ではなく、「介護サービスを安く受けられる制度」と覚えておくと良いでしょう。
もっと詳しく制度の全体像を知りたい方は、以下の厚生労働省のリーフレット(PDF)が参考になります。図解付きでわかりやすくまとめられています。
▶ 介護保険制度の公式リーフレットを見る(外部リンク)
介護保険が使えるのはどんな人?対象年齢と条件
介護保険の対象者は、以下の2つに分かれます。
● 第1号被保険者(65歳以上)
→ 年齢が65歳以上であれば、原因を問わず介護保険サービスを利用できます(例:転倒、認知症など)。
● 第2号被保険者(40~64歳)
→ 特定の病気(例:認知症、脳血管疾患など)で介護が必要になった場合に限り、サービスが使えます。
この記事では、特に親世代(65歳以上)を介護するケースを想定して解説しています。
要介護認定とは?介護サービスを受けるための最初の一歩
介護保険サービスを利用するには、「要介護認定」の申請が必要です。
これは、お住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターで手続きできます。
申請から認定までの流れは次の通りです。
- 市区町村に申請
- 調査員が本人を訪問し、日常生活の状況を確認
- かかりつけ医に「主治医意見書」を作成してもらう
- 専門家による審査会で、介護の必要度を判定
- 結果通知が届く(「要介護1〜5」「要支援1・2」「非該当」)
要介護度とは?7段階で介護の必要性が決まります
介護の必要度は次の7段階に分かれています。
- 非該当(自立)…介護保険は利用不可
- 要支援1・2…軽度の支援が必要
- 要介護1~5…数字が大きいほど重度の支援が必要
たとえば、
要支援1の方は週に数回の見守りや軽いサポート、
要介護5の方は24時間の全面的な介助が必要になるケースです。
利用できる介護サービスの例
介護保険を使って、以下のようなサービスが利用できます。
- 訪問介護(ホームヘルプ)
ヘルパーが自宅に訪問し、入浴や排泄、食事の介助を行います。 - デイサービス(通所介護)
施設に通い、食事・入浴・機能訓練・レクリエーションを受けられます。 - 福祉用具のレンタル・購入補助
車いすや介護ベッド、手すりなどの貸与や一部購入ができます。 - 短期入所(ショートステイ)
数日間施設で介護を受けることができ、介護者の休息にもなります。

申請してから使えるまでの流れと期間
申請後、通常は30日以内に結果通知が届きます。
その後、ケアマネジャーと相談しながら「ケアプラン(介護の設計図)」を作成し、介護サービスが正式にスタートします。
なお、すぐに介護が必要な場合は、暫定ケアプランを使って先にサービスを始めることも可能です。ケアマネジャーに相談してみましょう。
自己負担はいくら?注意すべき点
介護保険を利用する場合でも、サービス費用の一部は自己負担となり、原則1割(所得によって2〜3割)の支払いが必要です。
また、介護保険では「1か月に保険が適用されるサービス費用」の上限(支給限度額)が決められており、たとえば要介護1の場合はおおよそ月5〜6万円分までが限度となります。
※これは「サービス全体の費用」であり、自己負担額が5〜6万円という意味ではありません。
仮に1割負担であれば、自己負担は月5,000〜6,000円程度になります。
ただし、この上限を超えてサービスを利用すると、超えた分については全額自己負担(10割負担)となるため、注意が必要です。
さらに、施設サービスを利用する際には、介護サービス費のほかに「食費」や「居住費」などが別途かかり、これらは原則として実費(全額自己負担)になります。月額で数万円程度かかるケースも多く、利用前に費用の内訳を確認しておくことが大切です。
困ったときの相談先はどこ?
制度が複雑で「自分だけではわからない…」と感じたら、次の窓口に相談するのがおすすめです。
- 地域包括支援センター(地域に必ず1か所以上あります)
- 市区町村の介護保険課・高齢福祉課
- 居宅介護支援事業所(ケアマネジャーが在籍)
特に「地域包括支援センター」は、無料で相談できて親身に対応してくれるため、最初の相談先として最適です。
制度を知れば、介護はもっと安心できます
親の介護が始まると、不安や焦りで気持ちがいっぱいになってしまいがちです。
でも、制度を知っていれば、心にも時間にも余裕が生まれます。
最後に、この記事のポイントをまとめます。
- まずは「要介護認定の申請」からスタート
- 要支援・要介護度で使えるサービスが変わる
- 介護保険で訪問介護やデイサービスが利用可能
- 自己負担は原則1割、限度額を超えると負担増
- 迷ったら地域包括支援センターへ相談
介護は、「知らなかった」ことで損をするケースも少なくありません。
制度を正しく理解し、上手に活用することで、親の介護にも自分の生活にも、無理なく向き合っていきましょう。